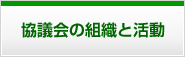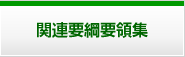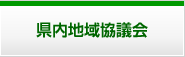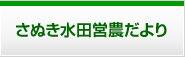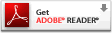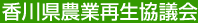トップ > 水田部会
経営所得安定対策|産地交付金|
畑作物産地形成促進事業及びコメ新市場開拓等促進事業
米の「生産の目標」|
水稲の生産振興方針|
旧香川県水田農業振興協議会ホームページ
経営所得安定対策
経営所得安定対策は、米・麦・大豆等の土地利用型農業の経営体の経営の安定を図ることを目的として実施しています。
制度の詳細は、農林水産省ホームページで紹介されています。
(注)平成27年産から、畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)及び米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)の対象者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者とされましたが、いずれも規模要件はありません。
県内の各地域農業再生協議会は、県内農業者の方が助成を受けるために必要な手続きの支援や現地確認等を実施しています。
産地交付金
産地交付金は、地域で作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づいて、①水田における麦、大豆等の生産性向上等の取組、②地域振興作物の生産の取組等を支援しています。
国から配分される資金枠の範囲内で、県や地域農業再生協議会が助成内容(交付対象作物・取組・単価等)を設定しています。
※令和7年度の県の交付金の内容・単価は、さぬき水田営農だより 111号をご覧ください。
畑作物産地形成促進事業及びコメ新市場開拓等促進事業
(旧新市場開拓に向けた水田リノベーション事業)
水田における畑作物の導入・定着により、水田農業を需要拡大が期待される畑作物を生産する農業へと転換するため、実需者との結び付きの下で、麦・大豆、高収益作物、子実用とうもろこし等の低コスト生産等に取り組む生産者を支援します。
制度の詳細は、農林水産省ホームページで紹介されています。
さぬきの米・麦
県内の米・麦の生産者を対象に、水田を有効活用し、需要に応じた作付拡大を進め、本県の水田農業の持続的発展を図ることを目的に推進大会を開催しました。
- 日時:令和7年8月8日(金) 午後1時30分〜午後4時20分
- 場所:丸亀市綾歌総合文化会館「アイレックス」大ホール(丸亀市綾歌町栗熊1680番地)
米の「生産の目標」
令和7年産主食用米の「生産の目標」について
「生産の目標」設定の考え方
全国の米穀情勢においては需給バランスが緩和されている中、本県では令和6年産主食用米の作付面積が10,000haを下回り、消費量が生産量を上回ることとなりました。
令和7年産の「生産の目標」については、県内消費量を県内で生産できるよう作付面積の増加に向け、県全体で設定します。
主要品種の生産の方向性
主食用水稲は、令和6年産実績より増産することを目標とし、令和5年産作付実績面積を数値目標として維持・増産します。
| 品種名 | 流通・販売状況と生産の方向性(JA香川県取扱より) |
|---|---|
| おいでまい | 約8割が県内向けに流通し、家庭用精米や学校給食用として使用されています。 ブランド化の取組みとして、良食味「特A」評価を再度獲得できるよう、品質の高位安定・向上に努め、香川県を代表するオリジナル米として、需要動向をみながら作付面積・生産量を増加させていきます。 |
| コシヒカリ | 約9割が県内向けの家庭用精米の定番として流通しています。 県内を主体に需要はありますが、温暖化による品質の低下が著しいため、全体作付面積は拡大しつつも、麦との二毛作を踏まえて水稲の中生品種や業務用途向けの主食用多収品種へ転換を図っていきます。 |
| ヒノヒカリ | 約7割が関西圏など県外向けに流通しています。食味が安定しており、年間を通じて主に業務用途での需要が多くなっています。 複数年契約の取組みを進めて販路を確保し、需要に応じた生産を進める必要があることから、作付面積・生産量を維持・増加させていきます。 |
| あきさかり | 主に県外業務用途向けとして導入しており、新型コロナウイルス感染症の影響により減退していた需要が回復してきたため、販路の拡大が進み、県内外で流通しています。(県内46%、県外54%) 複数年契約を含めた業務用途への販路拡大の取組みを強化し、需要動向を見ながら作付面積・生産量を維持・増加させていきます。 |
地域ごとの主食用米の生産の方向性(JA香川県各地域)
| 地域 | 主要品種・作付順 (下線はR6年産作付最多) |
生産の方向性 | |
|---|---|---|---|
| 作付面積 | 品種構成比率 | ||
| 大川 | コシヒカリ あきさかり ヒノヒカリ |
コシヒカリ:維持 あきさかり:増 ヒノヒカリ:維持 |
「コシヒカリ」に作付が偏っている(R6年産約72%)ため、主に「あきさかり」への品種転換を進め、将来的には「コシヒカリ」の構成比率を60%程度に抑制する。 |
| 中央 | ヒノヒカリ コシヒカリ あきさかり |
ヒノヒカリ:増 コシヒカリ:維持 あきさかり:増 おいでまい:維持 |
「コシヒカリ」の短期栽培の構成比率を減少させ、「あきさかり」(約14%)、「ヒノヒカリ」(約47%)への転換を行うとともに、「おいでまい」(約6%)は現状を維持する。 |
| 小豆 | コシヒカリ ヒノヒカリ |
コシヒカリ:維持 ヒノヒカリ:維持 あきさかり:維持 |
「コシヒカリ」(約57%)、「ヒノヒカリ」(約11%)、「あきさかり」(約5%)の構成で面積維持に努める。 |
| 綾坂 | コシヒカリ ヒノヒカリ おいでまい あきさかり |
コシヒカリ:維持 ヒノヒカリ:増 おいでまい:増 あきさかり:増 |
主要4品種の構成比率(「コシヒカリ」(約29%)、「ヒノヒカリ」(約22%)、「おいでまい」(約22%)、「あきさかり」(約20%))は維持する。 |
| 仲多度 | おいでまい コシヒカリ ヒノヒカリ |
おいでまい:増 コシヒカリ:維持 ヒノヒカリ:維持 あきさかり:増 |
「おいでまい」(約32%)は増、「ヒノヒカリ」及び短期栽培の「コシヒカリ」から「あきさかり」(約16%)への転換を行い、作期分散と作付面積の維持・増産に努める。 「コシヒカリ」(約28%)・「あきさかり」・「おいでまい」を中心として生産に取り組む。 |
| 三豊 | ヒノヒカリ コシヒカリ オオセト |
ヒノヒカリ:増 コシヒカリ:維持 オオセト :維持 あきさかり:増 |
「コシヒカリ」の構成比率を抑制し、「あきさかり」(約4%)、「ヒノヒカリ」(約48%)への転換を行うとともに、「オオセト」(約5%)の構成比率は維持する。 |
| 豊南 | コシヒカリ あきさかり ヒノヒカリ |
コシヒカリ:維持 あきさかり:維持 ヒノヒカリ:維持 |
「あきさかり」(約37%)、「コシヒカリ」(約41%)、「ヒノヒカリ」(約16%)の構成比率は維持する。 |
令和7年産の主食用米の「生産の目標」
※()の数値は生産の目標
| 生産の目標 | 【参考】 令和6年産(実績) |
【参考】 令和5年産(実績) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 (ヘクタール) |
生産量(見込) (トン) |
向き | 面積 (ヘクタール) |
生産量 (トン) |
面積 (ヘクタール) |
生産量 (トン) |
|
| 香川県 | 10,100 | 50,096 | ← | (10,100) | (50,096) | (10,800) | (53,568) |
| 9,770 | 48,000 | 10,100 | 50,200 | ||||
注1)「生産の目標」の生産量(見込)(トン)は、県の平年収量496kg/10aにより算定。
注2)農林水産省統計公表値
<参考>令和7年産の非主食用米の「生産の目標」
| 水稲の種類 | 令和7年産(目標値) | 令和6年産(10月現在) | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積(ヘクタール) | 向き | 面積(ヘクタール) | ||
| 香川県 | 加工用米 | 53 | ← | 53 |
| 米粉用米 | 8 | ← | 8 | |
| 飼料用米 | 190 | ← | 190 | |
| WCS用稲 | 350 | ← | 343 | |
| 新市場開拓用米 | 34 | ← | 34 | |
| 合計 | 635 | ← | 628 | |
- (参考)令和6年産主食用米の「生産の目標」(r6_mokuhyou.pdf|2ページ|113KB)
- (参考)令和5年産主食用米の「生産の目標」(r5_mokuhyou.pdf|2ページ|113KB)
- (参考)令和4年産主食用米の「生産の目標」(r4_mokuhyou.pdf|2ページ|118KB)
- (参考)令和3年産の主食用米の「生産の目標」(r3_mokuhyou.pdf|1ページ|119KB)
- (参考)令和2年産の主食用米の「生産の目標」(r2_mokuhyou.pdf|1ページ|153KB)
- (参考)令和元年産の主食用米の「生産の目安」(r1_meyasu.pdf|1ページ|45KB)
- (参考)平成30年産の主食用米の「生産の目安」(h30_meyasu.pdf|1ページ|75KB)
水稲の生産振興方針
平成30年産からの米政策の見直しに伴い、水稲生産、水田農業の振興に向けた具体的な取組など水稲の生産振興方針を定めています。米の全国的な需給状況や県下の主食用米の作付減少の状況を踏まえ、今後の水稲生産の振興に向け内容の改正を行い、水稲の作付面積・生産量の確保と需要に応じた生産を図ることとしました。
- 香川県水稲の生産振興方針(令和6年12月18日改正)(suito_houshin.pdf|5ページ|529KB)
旧香川県水田農業振興協議会ホームページ
香川県水田農業振興協議会は、平成23年5月30日に香川県担い手育成総合支援協議会と統合し、香川県農業再生協議会に改称・改組しました。
旧香川県水田農業振興協議会のホームページ
(掲載内容は更新されていませんのでご注意ください。)